失業手当がすぐもらえるかどうかは、多くの人が退職を考える際に直面する重要な問題です。
失業手当(正式には「基本手当」といいます)は、雇用保険の被保険者が離職した場合に、再就職活動を支援するために支給される給付金です。自己都合退職と会社都合退職では受給できる時期や金額に大きな違いがあり、
失業手当をすぐにもらえるかどうかは離職理由によって大きく左右されます。失業保険の受給期間や延長制度、必要書類、手続きの流れ、失業手当の計算方法、再就職手当についても詳しく解説します。
また、休職後や育休後の申請方法、病気による退職の場合の特例なども含め、ハローワークでの手続きをスムーズに進めるためのポイントをご紹介します。失業手当をすぐにもらうための条件や増額のテクニックも併せて解説するので、退職を検討している方は必見です。
失業手当をすぐもらえる条件と離職理由の影響

失業手当をすぐにもらえるかどうかは、離職理由によって大きく異なります。
会社都合と自己都合では、給付制限期間に違いがあるのです。
会社都合退職の場合
会社都合による退職(倒産・解雇・雇止めなど)の場合、
失業手当はすぐにもらえる可能性が高くなります。
具体的には、ハローワークへの求職申込みをして7日間の待機期間が経過した後から、失業認定日に認定を受ければ支給開始となります。つまり、早ければ退職後約1ヶ月程度で最初の失業手当を受け取ることができます。
会社都合退職と認められるケースは以下の通りです。
- 会社の倒産や事業所の閉鎖
- 人員整理などによる解雇
- 契約期間満了による雇止め
- 退職勧奨に応じた場合
- 労働条件が著しく変更された場合
自己都合退職の場合
一方、自己都合による退職の場合は、原則として7日間の待機期間に加えて、3ヶ月間の給付制限期間が設けられています。つまり、退職後約3ヶ月と1週間が経過してからでないと、失業手当を受け取ることができません。
ただし、自己都合でも「特定理由離職者」に該当する場合は、給付制限期間がなく、会社都合と同様にすぐに受給できる可能性があります。特定理由離職者に該当するのは以下のようなケースです。
- 体力の不足、心身の障害、病気などにより離職した場合
- 家族の介護のために離職した場合
- 妊娠、出産、育児などにより離職した場合
- セクハラ・パワハラなどが理由で離職した場合
- 事業所の移転により通勤が困難になった場合
| 離職理由 | 待機期間 | 給付制限期間 | 受給開始時期 |
|---|---|---|---|
| 会社都合退職 | 7日間 | なし | 約1ヶ月後 |
| 自己都合退職 | 7日間 | 3ヶ月 | 約3ヶ月+1週間後 |
| 特定理由離職 | 7日間 | なし | 約1ヶ月後 |
失業手当の受給期間と延長制度について詳しく解説
失業手当の基本的な受給期間は、原則として離職の翌日から1年間です。
この期間内に、被保険者であった期間や年齢に応じて決められた日数分の給付を受けることができます。
一般的な受給期間
被保険者期間と年齢によって、以下のように受給日数が決まります。
| 被保険者期間 | 30歳未満 | 30〜35歳未満 | 35〜45歳未満 | 45〜60歳未満 | 60〜65歳未満 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10年未満 | 90日 | 90日 | 90日 | 180日 | 150日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 | 180日 | 180日 | 240日 | 180日 |
| 20年以上 | 150日 | 210日 | 240日 | 270日 | 210日 |
会社都合による離職の場合は、より長い給付日数が設定されています。
受給期間の延長が可能なケース
以下のような理由で求職活動ができない期間がある場合、申請により受給期間を延長できることがあります。
- 病気やケガのため30日以上継続して就職できない場合
- 妊娠、出産、育児(3歳未満)のため就職できない場合
- 親族の介護のため就職できない場合
- 60歳以上の定年退職者が、失業給付よりも高い高年齢雇用継続給付を受けている場合
延長申請は必ず受給期間内(原則1年以内)に行う必要があります。延長できる期間は最長3年間です。
ハローワークでの手続きと必要書類についての完全ガイド
失業手当を受給するためには、ハローワークでの手続きが必要です。スムーズに手続きを行うために、必要書類と手続きの流れを理解しておきましょう。
必要書類の準備
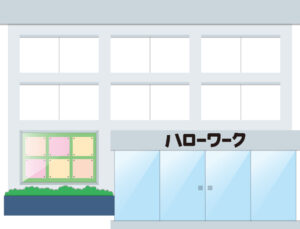
ハローワークに持参する必要書類は以下の通りです。
| 必要書類 | 備考 |
|---|---|
| 雇用保険被保険者証 | 退職時に会社から受け取ります |
| 離職票-1、離職票-2 | 退職後、会社から交付されます |
| マイナンバーが確認できる書類 | マイナンバーカードなど |
| 本人確認書類 | 運転免許証やパスポートなど |
| 写真2枚 | 縦3.0cm×横2.5cm |
| 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード | 振込先口座の確認用 |
離職票は退職後に会社から交付されるものですが、退職後すぐに交付されないケースもあります。
会社に交付を依頼しても交付されない場合は、ハローワークに相談しましょう。
手続きの流れ
| 手順 | 内容 | 時期 |
|---|---|---|
| 1. 求職申込み | ハローワークで求職申込みを行う | 離職後できるだけ早く |
| 2. 雇用保険説明会への参加 | ハローワークで開催される説明会に参加 | 求職申込み後、指定された日 |
| 3. 待機期間 | 7日間の待機期間が必要 | 求職申込み日から7日間 |
| 4. 給付制限期間 | 自己都合退職の場合のみ3ヶ月間 | 待機期間終了後 |
| 5. 失業認定日 | 約4週間ごとに失業の認定を受ける | 指定された日 |
| 6. 給付金の振込 | 指定口座に振り込まれる | 失業認定後、約1週間 |
自己都合退職の場合は、待機期間(7日間)の後に3ヶ月の給付制限期間があります。
会社都合退職や特定理由による離職の場合は、給付制限期間はありません。
失業手当の計算方法とシミュレーション
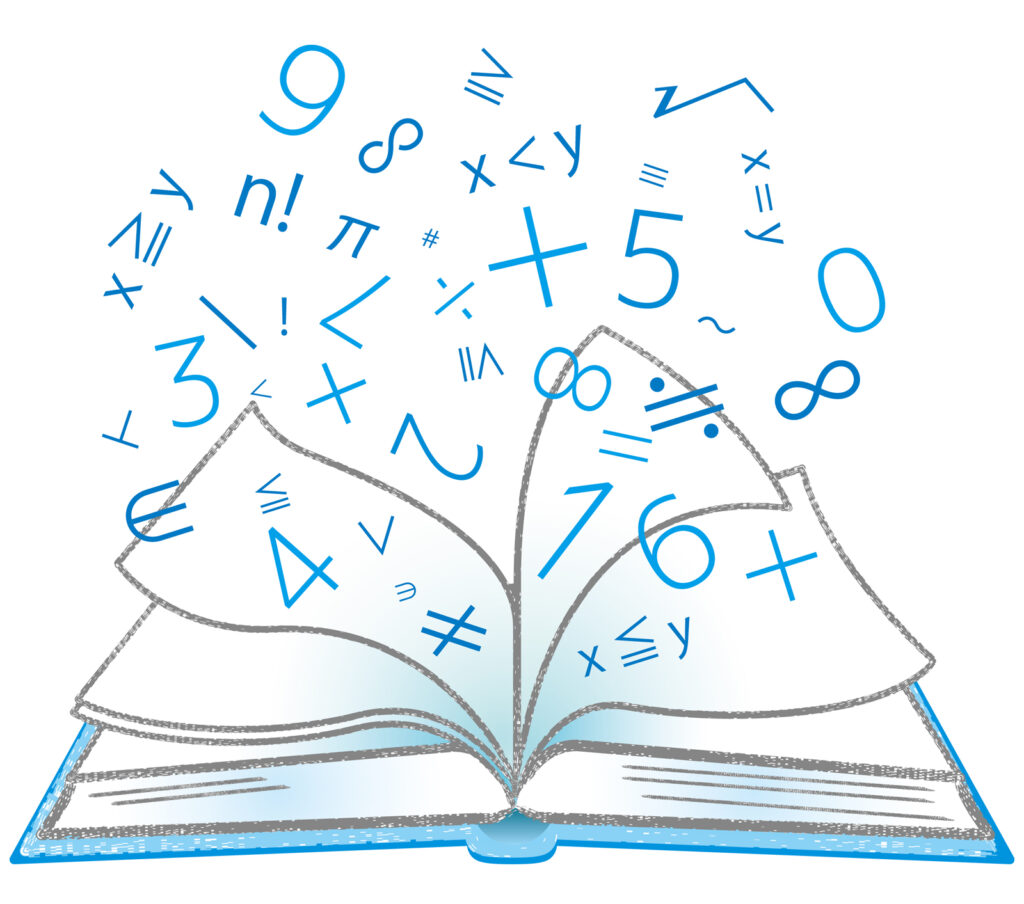
失業手当の正確な金額を知ることは、退職後の生活設計において非常に重要です。
ここでは、失業手当(基本手当)の詳細な計算方法とシミュレーション例を紹介します。
失業手当の基本計算式
失業手当は以下の3つのステップで計算されます。
| 計算ステップ | 計算式 | 説明 |
|---|---|---|
| 1. 賃金日額の算出 | 離職前6ヶ月の総支給額 ÷ 180日 | 離職前6ヶ月の給与・賞与などすべての支給額を合計し、180で割ります |
| 2. 基本手当日額の算出 | 賃金日額 × 給付率(45%〜80%) | 賃金日額に給付率を掛けます(給付率は賃金日額により変動) |
| 3. 月額の目安 | 基本手当日額 × 30日 | 基本手当日額に30を掛けると、月々の受給額の目安がわかります |
給付率の決定基準(2024年10月現在)
給付率は賃金日額によって変動します。低所得者ほど高い給付率が適用される仕組みになっています。
| 賃金日額 | 給付率 | 備考 |
|---|---|---|
| 2,574円以上5,030円未満 | 80% | 低所得者向けの高い給付率 |
| 5,030円以上12,630円未満 | 80%〜50% | 賃金日額に応じて段階的に低下 |
| 12,630円以上 | 50% | 高所得者は一律50% |
基本手当日額の上限
年齢によって基本手当日額の上限が設定されています。
| 年齢区分 | 上限額 | 月額換算(目安) |
|---|---|---|
| 29歳以下 | 7,435円 | 約22.3万円 |
| 30〜44歳 | 8,265円 | 約24.8万円 |
| 45〜59歳 | 9,069円 | 約27.2万円 |
| 60〜64歳 | 7,435円 | 約22.3万円 |
失業手当計算のシミュレーション例
例1:月給25万円の30歳会社員の場合
【計算手順】
-
賃金日額の算出
賃金日額 = 250,000円 × 6ヶ月 ÷ 180日 = 8,333円 -
給付率の適用
給付率 = 約65%(賃金日額が8,333円の場合) -
基本手当日額の算出
基本手当日額 = 8,333円 × 65% = 5,416円 -
月額の目安
月額の目安 = 5,416円 × 30日 = 162,480円
この場合、月に約16万円の失業手当を受け取ることができます。
被保険者期間が10年未満で30歳なら、90日分(約49万円)が支給される計算です。
例2:月給40万円の50歳会社員の場合
【計算手順】
-
賃金日額の算出
賃金日額 = 400,000円 × 6ヶ月 ÷ 180日 = 13,333円 -
給付率の適用
給付率 = 50%(賃金日額が12,630円以上のため一律) -
基本手当日額の算出
基本手当日額 = 13,333円 × 50% = 6,666円 -
月額の目安
月額の目安 = 6,666円 × 30日 = 約200,000円
この場合、月に約20万円の失業手当が支給されます。
ただし、45〜59歳の上限額は9,069円なので、上限を超えません。被保険者期間が20年以上であれば、270日分(約540万円)の支給になります。
賞与・残業代も含めた正確な計算方法

実際の計算では、以下の収入も含めた総支給額を基準に算出されます。
| 含める収入 | 備考 |
|---|---|
| 基本給 | 毎月の基本給 |
| 各種手当 | 住宅手当、家族手当など |
| 残業代 | 時間外労働の割増賃金 |
| 賞与・ボーナス | 直近6ヶ月に支給された分 |
一方、以下のような金額は賃金日額の計算に含めません。
| 含めない収入 | 備考 |
|---|---|
| 退職金 | 離職に伴い一時的に支払われる金額 |
| 結婚祝金など | 一時的な祝い金 |
| 通勤手当(非課税限度額内) | 実費弁償的な性格のもの |
2025年3月現在、失業手当の増額が検討されているとの情報もありますので、最新の給付率や上限額については、ハローワークで確認することをおすすめします。
また、オンラインでも簡易的なシミュレーションができるツールが提供されていますので、自分の状況に合わせて試算してみるとよいでしょう。
給付金額シミュレーションサイトはこちら👇
退職サポートサービスと再就職手当の活用法
失業期間を有効に活用するためには、さまざまなサポートサービスの利用や再就職手当の活用が効果的です。

退職サポートサービス
近年は、退職に関するサポートを行う民間サービスも増えています。
これらのサービスでは、以下のようなサポートを受けることができます。
| サポート内容 | 詳細 |
|---|---|
| 退職交渉のアドバイスや代行 | 円満退職のための交渉戦略や代行サービス |
| 退職後の手続きに関するサポート | 失業保険や健康保険などの手続きのアドバイス |
| 失業手当の申請サポート | ハローワークでの手続きをスムーズに進めるサポート |
| 転職活動のコンサルティング | 効果的な転職活動のためのアドバイス |
退職サポートサービスを利用するメリット

- 精神的負担の軽減:直接の対面交渉による精神的ストレスを回避できる
- 円満退職の実現:専門知識を持つ第三者が間に入ることで、感情的な対立を避けられる
- 条件交渉の最適化:退職金や有給消化などの条件交渉を有利に進められる可能性がある
- 書類作成の適正化:離職票の記載内容を適正化し、失業手当の受給に有利な形に調整できることも
- 退職後の手続きの効率化:健康保険、年金、税金など各種手続きのガイダンスが受けられる
退職サポートサービス選びのポイント
- 実績と評判の確認:口コミや成功事例数を確認する
- 提供サービスの範囲:単なる退職代行か、その後のサポートまで含むかを確認
- 費用対効果:料金プランと提供サービスの内容を比較検討する
- 専門家の関与:弁護士や社労士など有資格者が関与しているかを確認
- アフターフォロー:退職後の手続きや再就職支援などのフォロー体制を確認
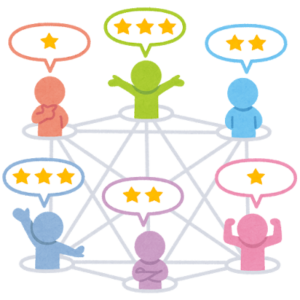
特に会社との関係が悪化しているケースや、退職理由によって失業手当の受給に影響がある場合は、
専門家のアドバイスを受けることで不利益を被るリスクを減らせる可能性があります。
退職サポートサービスは有料のものが多いですが、トラブルを避け、スムーズな退職と次のステップへの移行をサポートしてくれます。利用を検討する際は、自分の状況と必要なサポートレベルを見極めて、。最適なサービスを選ぶことが重要です
再就職手当の活用

失業給付の受給資格者が、支給日数の残りが所定給付日数の3分の1以上ある状態で再就職した場合、
再就職手当を受け取ることができます。
| 支給残日数 | 再就職手当の金額 |
|---|---|
| 所定給付日数の3分の2以上の場合 | 基本手当日額の70%×残日数 |
| 所定給付日数の3分の1以上3分の2未満の場合 | 基本手当日額の60%×残日数 |
例えば、基本手当日額が8,000円、所定給付日数が120日の場合で、40日分を受給した後に再就職した場合: 残りの給付日数は80日で、所定給付日数の3分の2以上あるため、8,000円×70%×80日=448,000円の再就職手当が受け取れます。
再就職手当を受け取るためには、以下の条件を満たす必要があります。

- 失業給付の受給資格がある
- 安定した職業に就いた(1年以上雇用される見込みがある)
- 離職前の事業主に再雇用されたものでない
- 過去3年以内に再就職手当の支給を受けていない
早期に再就職することで、失業給付と再就職手当の両方を効率的に活用できる可能性があります。
休職後・育休後の失業手当申請と病気退職の特例
特殊なケースとして、休職後や育休後の退職、病気による退職の場合の失業手当申請について解説します。
休職後・育休後の失業手当

休職や育休から復帰後に退職する場合も、通常の退職と同様に失業手当を申請できます。ただし、以下の点に注意が必要です。
| 状況 | 注意点 |
|---|---|
| 育児休業給付金の受給期間 | 失業手当の算定対象期間から除外される |
| 休職中の給与減額 | 失業手当の金額に影響する可能性あり |
| 病気休職を理由とした退職 | 「特定理由離職者」として給付制限なしの可能性あり |
育休後に子育てのために退職する場合は、「育児のための離職」として特定理由離職者に該当する可能性があるため、ハローワークで相談することをおすすめします。
病気退職の特例
病気やケガが原因で退職する場合、「特定理由離職者」として扱われ、自己都合退職であっても給付制限期間(3ヶ月)なしで失業手当を受給できる可能性があります。
| 特定理由離職者と認められる条件 | 詳細 |
|---|---|
| 病気やケガによる就労不能 | 働くことができない状態であること |
| 状態の継続性 | その状態が退職時まで継続していること |
| 証明書類 | 医師の意見書など、病状を証明する書類があること |
ただし、退職後すぐに就労可能な状態であれば、特定理由離職者として認められない場合もあります。また、病気が治った後に失業認定を受ける必要があるため、治療期間中は受給期間の延長申請をしておくとよいでしょう。

まとめ
失業手当(基本手当)は、再就職活動を支援するための重要な制度ですが、受給条件や申請方法を正しく理解することが大切です。
本記事のポイントをまとめると:
- 失業手当の受給時期は離職理由によって異なり、会社都合退職や特定理由離職では約1ヶ月後から、自己都合退職では約3ヶ月後からとなります。
- 受給期間は原則1年間で、被保険者期間と年齢に応じて90日~270日の給付日数が設定されています。
- 病気・育児・介護などの理由がある場合は、受給期間の延長が可能です(最長3年)。
- 手続きはハローワークで行い、離職票や本人確認書類などの必要書類を準備する必要があります。
- 失業手当の金額は、離職前6ヶ月の賃金を基に計算され、賃金日額に応じた給付率(45%~80%)が適用されます。
- 再就職手当を活用すれば、早期に再就職した場合でも残りの給付日数の60%~70%を一時金として受け取れる可能性があります。
- 病気退職や育児のための退職は「特定理由離職者」として給付制限なしで受給できる場合があります。
失業手当の申請は、自分の状況に合わせた最適なタイミングと方法を選択することが重要です。
不明点があればハローワークでの相談を活用し、退職後の生活の安定と円滑な再就職に向けて、制度を有効に活用しましょう。


